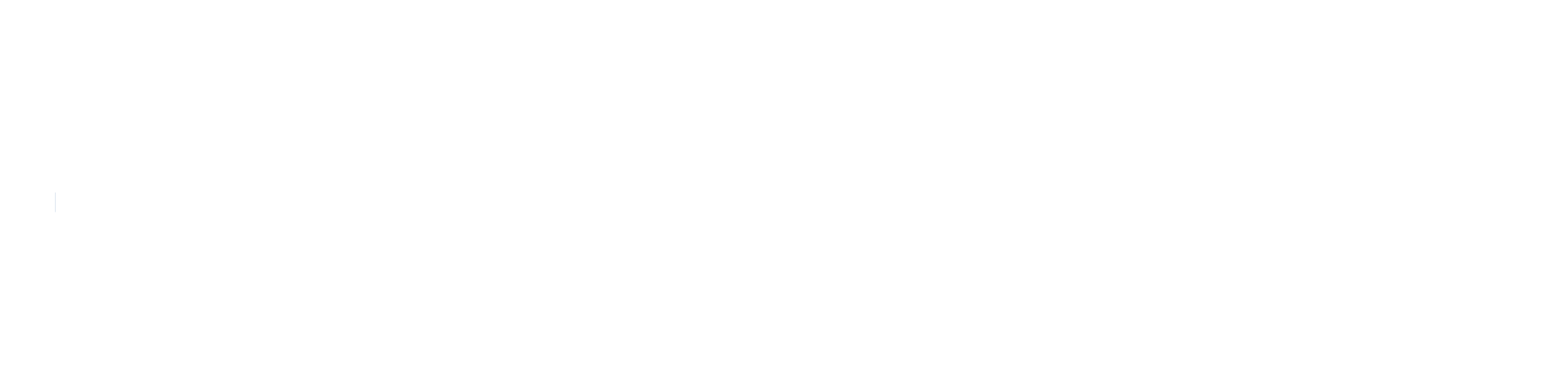コミュニケーションのプロセスは、メダルの表裏のようなものです。自分の表現方法がコミュニケーションの片面であり、人の捉え方がもう片面です。では、相手が何を感じ、何を求めているのかを理解するには、どうすればよいのでしょうか。
この問いに対して多くの人が出す答えは、「共感」でしょう。共感とは、私たちが日常生活で頻繁に使うフランス語起源の言葉で、トルコ語協会では「他人の気持ちを感じる」と定義されています。トルコ語版の言葉を知らない人が多いほど、私たちの言葉に根付いています。
調停や交渉のプロセスにおいて(特に家族調停など感情的な結びつきの強い調停プロセスにおいて)、「相手が共感してくれない」という不満がよく聞かれます。日常生活においても、調停と同様に、共感は「期待」されていることが多い。つまり、共感は相手から期待される行動であって、人を理解するための方法ではないことが多いのです。しかし、非暴力的なコミュニケーションは、こちらも共感してこそ成り立つものです。
都会の生活が人に与える衝動には、「早く」というものがある。食べ物は早く食べなければならないし、仕事は早く終わらせなければならないし、今日と同じように次の日を迎えるために一日を急がなければならない。人は、私たちが用意した時間を超えてはいけないのです。このようにスピードを求めると、その人の気持ちを理解しようとするよりも、その人が何を必要としているかをすぐに見つけ出してしまいがちです。共感とは、問題を素早く察知して、相手を慰めたり、助言したりすることです。例えば、ある人が悩みを打ち明けたとき、私たちは「そのうち治るよ、そんなに心配しなくても、きっと乗り越えられるよ、あなたは私が今まで会った中で一番強い人だよ」という慰めか、「きっと・・・するといいと思うよ、・・・」というアドバイスのどちらかをする傾向がある。
しかし、共感のプロセスで最も重要なのは、理解しようとしている相手に時間を与えることです。人は多くの場合、アドバイスや慰めの言葉を聞く必要はなく、ただ理解されたと感じることが必要なのです。 相手が言いたいことをすべて言ったと確信できるまで話を聞いてあげると、相手とのコミュニケーションが深まります。相手の言いたいことを正確に理解し、気持ちを伝えるためには、「では、この状況であなたはどう感じましたか、こんなときどうされたいですか」など、オープンエンドな質問をすることが有効です。私たちが理解していることが、必ずしも相手の言いたいこととは限りません。また、理解したことを自分の言葉に反映させ、その正確さを確認することも有効であろう。そうすることで、誤解していた点が明確になります。
非暴力的なコミュニケーション・プロセスのためには、自分の気持ちやニーズを十分に表現できることと、相手の気持ちやニーズを理解できることが基本であり、これはメダルの表と裏の関係にある。そのためには、共感を「期待する」行動ではなく、「実践する」行動にしていきましょう。
ローゼンバーグ、マーシャル・B.『非暴力コミュニケーション 人生の言葉』、2015年 p.110-146.
アルツムベイザÇメン