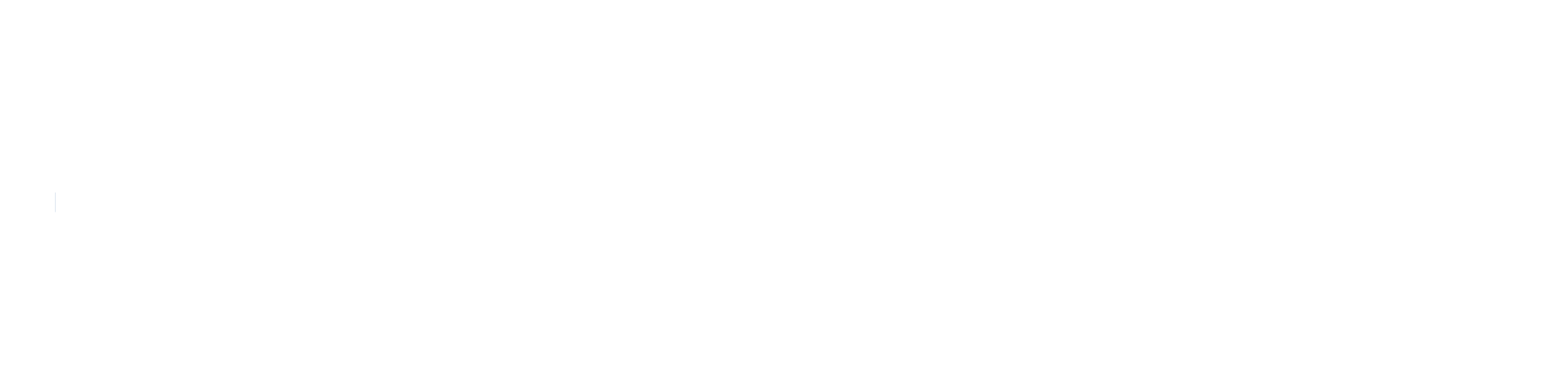効果的なコミュニケーションは、調停プロセスの成功のための最も重要な要素と考えることができます。当事者がしばしばコミュニケーションの重要性を真剣に考えない場合、調停者は主に2つの理由からそれに注意を払うよう誘われる。
当事者間の良好なコミュニケーションは、建設的な方法で関与することを可能にし、交換を促進します。そうすることで、当事者間にダイナミズムが生まれ、調停人は紛争のさまざまな側面をよりよく理解できるようになり、適切な解決に向けた道筋や選択肢の開発が促進されるのです。
コミュニケーションの有効性を追求することは、プロセスを通じて続く定期的な作業です。コミュニケーションが効果的であればあるほど、合意形成は容易になります。この意味で、仲介者の役割は非常に重要です。仲介者は、プロセスの各段階において、当事者間のコミュニケーションを促進するあらゆる手法を導入するよう心がけなければなりません。
調停における効果的なコミュニケーションとは?
説得の要素だけでなく、その際に優位となる感情や文化的な側面も考慮したコミュニケーションである。
説得の要素。
説得につながるコミュニケーション戦略は、アリストテレスの類型論に従って分析することができる。ロゴス、エトス、パトス[1].ロゴスとは、伝達されるメッセージの実体である。したがって、当事者が伝えたい論拠や具体的なアイデアである。エトスとは、話し手の信頼性や権威を指し、パトスとは、話し手が聴衆に喚起するために管理する感性のことである。
しかし、コミュニケーション戦略の目的が、いかなる聴衆をも説得することであるならば、ロゴス、エートス、パトスの理想的なバランスを達成する必要がある。もう一つ考慮しなければならないのは、通常の裁判における説得は、それが裁判であれ仲裁であれ、調停手続における説得とは異なるという事実である。裁判では、さまざまな当事者のコミュニケーション戦略の目的は、手続き法に関する伝統的な証明手段を用いて、裁判官を説得し、その結果、彼らの主張のメリットを納得させることである。そして、紛争の解決は、それぞれの当事者間の対立の論理に従って行われる。
調停プロセスでは、当事者も同じゲームをする傾向があり、調停委員に自分が "正しく"、相手が "間違っている "と納得させようとするのです[2].しかし、調停の本質が当事者間の協力の精神を必要とするのであれば、説得もまた別の形で考えなければならない。共通の目的に向かって個々のニーズや目標を共有するためには、自分も相手もそれぞれの立場から離れ、共通の利益に向かってコミュニケーションの努力を集中させるよう説得することが必要である。
感情面
紛争は、感情的な要素が支配的です。どんな紛争でも、人々は感情を帯びていることを意味します[3].そして,感情の外在化を感じることができる紛争は,特定の分派に限定されるものではない.家族、相続、近所付き合い、ビジネスや職場に関するものなど、すべての紛争に感情が込められているのです。[4] 様々な形で
この感情的な側面によって、紛争の裁判上の解決と、主に調停による裁判外の解決との違いを確立することができる。司法による解決や仲裁は、「縦の関係」に従って進められるため、紛争の感情的な側面を軽視する傾向がある。裁判所の判決や仲裁判断の探求は、主に紛争の事実的・法的要素に焦点を当てることによって行われる。
一方、紛争を解決するために調停を選択することで、紛争をその対象に応じて特定し、対処することが可能になりますが、同時に、当事者間の関係に応じて、紛争を特定し、対処することも可能になります[5].その理由は簡単で、次のように構成されている。それは、調停プロセスにおける「関係の水平性」によって、当事者のみが解決策を見出すことができるようになるためである。したがって、紛争の本質を構成する解決すべき問題を、個人とその関係から切り離すことは困難である[6].後者は実際、感情によって条件づけられ、その感情は紛争の起源となり、その結果を構成することができる。
文化的側面
最近、紛争の文化的側面が特に注目されている[7].広義の文化には、国籍、民族、宗教、政治的イデオロギーなどが含まれる。調停プロセスにおいて、文化の違いはそれぞれの当事者間の関係だけでなく、当事者と調停者である第三者との関係においても分析することができる。しかし、仲介の際に考慮すべきこの文化的側面とコミュニケーションとの間にはどのような関係があるのでしょうか。答えは明らかです。文化の違いは誤解を生み、コミュニケーションを困難に、あるいは不可能にし、すでに生まれている対立をさらに深めたり、別の対立を生み出したりする可能性があるからです。したがって、文化的なギャップが大きければ大きいほど、誤解が生じるリスクが高くなり、コミュニケーションが難しくなり、合意に至る可能性も低くなる。しかし、これは国家間、民族間、共同体間の紛争に限ったことではなく、文化やビジネス倫理の乖離が問題となる国境を越えた商取引上の紛争にも適用される。
ここでも、紛争解決の手段として調停を選択することで、当事者は、伝統的な司法手段によって紛争を終わらせることを選択した場合には決して直面することのない追加的な要素を考慮することになるのである。したがって、調停の有効性が各当事者が相手の利益を理解し、評価する能力に依存するとすれば、この理解を可能にするためには、文化的側面を考慮する必要がある。ここで、調停人の役割が大きく役立つことになります。
十分なコミュニケーション環境を整えるために、3つの側面から検討すること。
当事者間のコミュニケーション不足は、紛争の原因となるばかりでなく、既に生じている紛争を悪化させることもある。従って、紛争を理解する上で、調停人のコミュニケーションの資質とスキルの重要性を無視することはできません。その結果、当事者は建設的な意見交換を行うことができ、合意に達することができるのです。しかし、効果的なコミュニケーションのための適切な環境を作るには、まず、調停人が説得、感情、文化の3つの要素を考慮することが必要です。

説得力のある側面からの考察
効果的なコミュニケーションには、ロゴス、エートス、パトスの各要素のバランスが必要であるとすれば、これは調停者側の効果的な介入によってのみ達成されるものである。実際、当事者は3つの要素のうち1つを疎かにしてしまい、コミュニケーションを難しくしてしまうことがあります。ここに、調停が当事者間の交渉に与える「付加価値」を見ることができます。公平中立な第三者の介入により、当事者だけでは乗り越えにくい様々な障害を克服することができるのです。このような障害の中には、プロセスの進展を妨げる効果的でないコミュニケーションを挙げることができます。
交渉を望ましいゴールに向かわせる、元の対立状況から生まれる緊張を和らげる、相互の立場をまとめ、共通の利益を確認する、など、調停者側には説得の要素に重点を置いたコミュニケーション技術が必要です。[8].説得の効果は、仲介者(説得の主体)のコミュニケーションがどのように当事者に伝わるか、すなわち、行われた直接・間接の説得の試みが当事者の将来の行動に影響を与えるか、あるいは影響を与えるかどうかにかかっている[9].
したがって、調停プロセスでは、説得的な側面を考慮することが最も重要である。説得力のあるコミュニケーションは調停者から始めなければなりませんが、調停者が利用できるツールは非常に多様で、想定される調停の種類や調停者の性格によって異なります。
感情面への配慮
紛争関係は、法的、心理的、感情的な側面から構成されています。この最後の次元は、調停者の側で注意深く介入する必要があります。実際、否定的な感情の動きを避けながら、当事者が自分の感情を表現できるようにすることで、解決策を見出す段階へ容易に進むことができるようになります。[10].この移行期にこそ、調停者の感情的な知性が違いを生み出さなければなりません。感情から理性に行くことは、協力的な環境のインストールのための強固な基盤を構成することになり、調停者は、紛争の問題を特定し、当事者がそれぞれの利益に焦点を当てることができます[11].
葛藤や感情の源は、過去に起きた出来事に由来しています。そのため、問題解決のための探求は、そのきっかけを理解することから始めなければならない。このとき、メディエーターに必要なのは「傾聴」であると分析される。
しかし、当事者を過去から切り離し、未来に向かわせることが第二段階である。ここで、調停人が感情的な側面に配慮することが、違いを生むことになります。当事者にページをめくるように促すことで、中立性が保たれるのです。[12] と、メディエーターが自分の感情をコントロールする能力が大きな関心事であり、プロセスの運営に不可欠な要素を構成しています。[13] と調停を成功させることです。
文化的側面への配慮
効果的なコミュニケーション戦略には、文化の違いをうまく管理することが必要です。そのため、調停人は、調停プロセスの開始前に上流で、また調停中に下流で行動することができるようになります。
文化的な側面を考慮に入れてコミュニケーションの難しさを予測することは、紛争当事者間の文化的なギャップを測定することによって上流で行われる。この点で、調停に奉仕するデジタル技術はその面白さを十分に証明しています。実際、文化的差異を測定する人工知能とアルゴリズムの利用により、調停人は直面する紛争ごとに「パーソナライズされた文化地図」を構築することができるようになる。[14].
各当事者の文化的価値観を理解することで、プロセスの過程で当事者間のコミュニケーションへの悪影響を抑えるために、潜在的な行動の落とし穴を調停者が予期することができます。
下流で、成功するコミュニケーションは、すでにつかみどころがない。そこに多文化という次元が加わると、この困難さはさらに際立ちます。[15].言語と、言語および非言語コミュニケーションに対する当事者の考え方の2つが主な障壁となる中[16]また、文化的な違いから、利害が対立することもあります。従って、調停人はこれらの文化的問題に特有のテクニックを採用する必要性を認識し、それらを乗り切るためのツールを身につける必要があります。[17] 一方では、文化的な問題など、紛争の本質とは無関係な問題を評価するための調停前会議、他方では、相手に対する各当事者の文化的理解を評価するためのコーカスセッションが行われます。
[1] ARISTOTLE「アリストテレスのレトリック」参照。
[2] J. H. STARK, D. N. FRENKEL, "Changing Minds:メディエーターの仕事と説得の実証研究」『ペンシルバニア法学』(Penn Law:Legal scholarship repository, 2013, p.266.
[3] P-C.LAFOND, "La prise en considération des émotions en médiation : une intervention essentielle et delicate", Les Cahiers de droit, Volume 61, numéro 4, décembre 2020, p.937-958.
[4] A.ZARISKI, "Senti alteram partem:司法調停における権利、利益、情熱、感情」『仲裁調停ジャーナル』第4巻第2号、2013年、1-6頁。
[5] W.URY, R. FISHER, B. PATTON, "Comment réussir une négociation", Paris, Seuil, 2006, p.43-45.
[6] C.MENKEL-MEADOW, "Chronicling the Complexification of Negotiating Theory and Practice", Negotiation Journal, vol.25, no 4, 2009, p.415-416.
[7] K.LUCKE, A. RIGAUT, "Cultural Issues in International Mediation", p.4, 2002. https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/ctccs/projects/translatingcultures/documents/journals/cultural-issues-mediation.pdf
[8] J. H. STARK, D. N. FRENKEL, op. cit, p. 271.
[9] E.ARONSON, "The Power of Self-Persuasion", 54 AM.Psychologist 875-84 (1999).
[10] E.ファスティング、「脳を敵ではなく味方にする:介入者が神経科学について知っておくべきこと」、アメリカン・ジャーナル・オブ・メディエーション、6巻、2012年、47 - 60頁。
[11] C.CHICVAK, "Concretizing the Mediator's Je Ne Sais Quoi: Emotional Intelligence and the Effective Mediator", American Journal of Mediation, vol.7, 2013-2014, p.14.
[12] T.S. JONES, Andrea BODTKER, "Mediating with Heart in Mind:調停実践における感情への対応」『交渉学雑誌』17巻、2001年、220頁。
[13] R.A. DEMAYO, "Practical and Ethical Concerns in Divorce Mediation:R. A. DEMAYO, "Practical and Ethical Concern in Divorce Mediation: Attending to Emotional Factors Affecting Mediator Judgment", Mediation Quarterly, vol.13, no 3, 1996, p.221, 222, 224.
[14] Hofstede Insightsとして知られるGeert HOFSTEDEによる実証研究を参照。
[15] K.LUCKE, A. RIGAUT, op.cit, p.15.
[16] V.STESIN, "How do cultural differences influence mediation?", Wolters Kluwer, 21 February 2022.
[17] P.SINGH, "A mediator's guide for navigating a cross-cultural mediation", Ex Curia International, 2021, https://excuriainternational.com/2021/06/25/a-mediators-guide-for-navigating-a-cross-cultural-mediation/