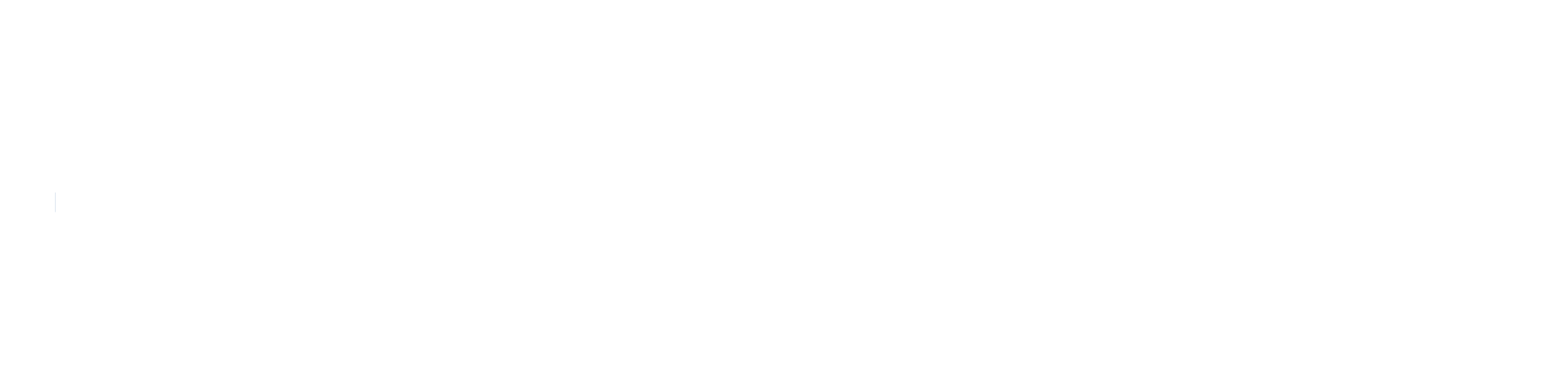COVID-19の流行と調停者訓練への短期的影響 2020年2月以前、私たちの調停訓練は、世界の他のほとんどの調停訓練と同様に、現場で行われました。すべてが機敏で順応性があるように見えましたが、1つだけ決まっていることがあります--研修は常に現場で行われるのです。私たちの研修に参加する調停人は、幹部、人事部長、常務取締役として、調停の実施方法とチームでの調停手法の適用方法を学びます。そのため、会社やスタジオ、オフィスなど、現場で行われることが前提でした。もちろん、オンライン紛争解決(ODR)については知っていたし、調停会議でオンライン調停を宣伝するブースを見かけたこともあった。私たちの一般的な評価は、これは興味深いけれども、関連性のないニッチな分野だということでした。ところが、すべてが変わりました。
昔の "ノーマル"
調停訓練は合計4ヶ所(シュトゥットガルト、ハンブルク、ベルリン、ミュンヘン)で行われ、通常、すべての場所で年に2回開催されます--少なくとも、COVID-19以前はそうでした。研修は、ドイツ調停研修法の仕様と基準に基づいています。120時間です。3日間かけて5つのモジュールに分かれています。5ヶ月後には、参加者はメディエーターとして認定されます。研修グループの人数は、10人から15人です。

変遷 - "必要なこと"
2020年2月から新しい対面式コースが始まる予定だった。COVID-19は、変化の必要性を訴え始めたが、新コースの最初のモジュールは、通常通り現場で行われた。その後、ウイルスが発生し、公共スペースで3人以上と会うことが禁じられた。今度はどうするか?社内で協議した結果、これまで不可能とされていたこと、つまりオンラインで調停を教えることにしました。
評価
私たちの組織の指針は、トレーニングの質を優先させることです。私たちは、継続的な評価と品質向上に取り組んでいます。個別フィードバックセッションに加え、各モジュール終了後には、モジュール内容、講師、グループの状況に関する評価と、受講者の学習進捗状況に関する評価の2つの評価を実施しています。さらに、講師は各モジュール終了後、受講者個人に対する評価も行っています。また、講師には、グループに対する認識、学習の進捗状況、コミットメント、知識レベルについて定期的に質問しています。このデータのコーパスは、新しいフォーマットを評価し、他のフォーマットと比較することも可能にしました。

この図は、すべてのトレーニング形式の平均評価を示しています。
[cid:0B5582BEDF6E4C2DA5D2A54CB4F728A5]
非常に高いレベルで、オンライントレーニングはハイブリッドよりも、オンサイトトレーニングよりもさらに優れていると評価されました。オンサイト形式とオンライン・トレーニングは、このように参加者が選択し、予約したものです。参加者がどのようにトレーニングを探し、どのように受け取ったかについて、ここでは最も完全な一貫性があった。
この高い受容性の一つの仮説は、このフォーマットを使用することを参加者が自己決定したことであると考えられる。この緊急事態において、現場での指導からオンラインに変更することについて、参加者と詳細に話し合いました。このフォーマットで訓練を継続することをグループ自身が決定したのです。これは、当初期待され、予約されていたものとかなり違っていたとしても、このトレーニングに対する肯定的な評価につながるコミットメントであった可能性がある。
オンライン・トレーニングの評価が高いのは、参加者が積極的にこの形式を選択したことも関係していると思われる。参加者は、オンライン・トレーニングか、少し遅れて開催されたオンサイト・トレーニングのどちらかを選択することができました。そのため、この形式を選んだ参加者は、積極的にオンラインを選び、高い評価はこの形式を好んだことを反映しているのかもしれません。

オンラインとオンサイト。メリット
参加者から2つの形式の特徴をより深く知るために、ハイブリッド・モジュール終了後に追加のアンケートを作成した。これらは、参加者がオンサイトとオンラインのフォーマットの利点と欠点をどこに見ているかという質問に特化した公開質問を含んでいた。その結果を回答頻度の高い順に以下の表14.3に示す。両方の形式を経験した 40 名の参加者には、自由形式の質問票によるインタビューが行われた。
[cid:CA94BAEAFB2948869D27C970EE5E9DCB]
[cid:8DA23FED1AEA4853AB69651FCC178581][cid:EEF25D3A81B94806AD4568B1EB6E7517]
アンケートの結果は、最後のモジュールで参加者と議論され、そこからさらに説明がなされました。全体として、オンライン形式の利点は、オンサイト形式の2倍の言及があった。その後の定性的な質疑応答では、現場での授業が普通であり、デフォルトであると考えられていることが明らかになった。
受講者は、オンラインレッスンにおける集中力の向上が最大のメリットだと考えている。全体の半数以上が、授業や内容、演習、またシミュレーションなどでは他の参加者への集中力が高まったと回答しています。また、参加者は、画面上で起きていることすべてが視界に入り、注意力が高まったと感じているようです。私たちのトレーニングでは、「カメラをつける」ことが義務づけられているのです。また、参加者からは、常に自分の姿が見え、皆のすぐ近くに見えることで、集中力を持続させ、気が散らないようにせざるを得なかったという声も聞かれました。一方、現場では、気が散ることもありますし、部屋の中では常に動きがあり(誰かが立ち上がる、トイレに行く、コーヒーを飲むなど)、集中力が散漫になります。

2つ目の利点は、オンライントレーニングでは、コンテンツを提示するためのメディアの組み合わせが多いことで、これも集中力の向上と関連していると述べた。プレゼンテーションには、ビジュアルコンテンツ、インタラクティブクイズ、フィルムクリップ、グループワークなどが含まれ、参加者は、オンサイトの教室で同様の方法を適用するよりも変化に富んでいると感じたと報告しています。例えば、教室のスクリーンに映し出された内容よりも、パソコンの画面に映し出された内容の方が近くて見やすいので、見ていて気持ちがいいという意見もありました。
また、半数近くが、シミュレーションでは相手の表情がより観察しやすいことを、オンライン空間での利点として挙げている。会話はより直接的で即時性があり、発言と表情だけのボディランゲージとの整合性に疑問を感じることが少なかったという。会話では、オンライン環境の方が相手を読み取ることができたという。また、自分の環境に身を置くことの気持ちよさも影響しているようです。自分の食事を作る」「好きなお茶を飲む」「座り心地の良い椅子」「楽な服装」などが挙げられています。また、「時間管理がしやすくなった」という意見も17件ありました。特に強調されていたのは、「家に直接いること」と「レッスン終了時に移動する必要がないこと」。また、授業は週末に行われるため、「週末に何か残っている」というトピックも一役買っている。
私たちにとって驚くべき問題は、さらに定量的に調査する予定ですが、参加者が、オンライン形式の方が全員が効果的であるという印象を抱いていることです。例えば、参加者の約4分の1がオンライン形式のポジティブで有利な点であると感じている「過剰に長いスピーキングターンがない」という意見が複数ありました。しかし、この点についてトレーナーに質問したところ、オンライン形式でも会場形式でも、個人の発言ターンの長さに観察できるほどの違いは感じられなかったそうです。しかし、オンラインレッスンでは、中断が少ないため、教材がより早く伝わったとトレーナーは感じているようです。一方、オンサイト・トレーニングでは、長い議論を中断してまでプログラムを進めなければならないと感じることが多くありました。
オンライン形式の最後の利点は、グループ内の規律がより高いという認識でした。オンライン形式では、中断があまりなく、参加者はより時間を守るようです。この点は、特に休憩後の授業開始時間に関連しています。オンサイト形式では、コーヒーマシンでの会話が非常に面白く、すべての会話が終わらないことがしばしばありましたが、オンライン形式では、参加者は授業再開の時間通りに戻ってきました。これはトレーナーの観察とも一致しています。

オンサイトフォーマットの利点
次に、会場型の利点についてだが、参加者が会場型の最大の利点として挙げたのは、まさにこのコーヒーマシンでの会話や個人的な出会いであった。休憩時間に意見交換をしたり、お互いのことをよく知ることができ、貴重なネットワークが構築できたと述べている。また、参加者の目には、休憩時間中のディスカッションがグループ内や個人間の信頼関係につながり、学習の良い基盤になっているように映ったようです。例えば、間違いを犯したり、自分の目から見て「バカ」であることは、コースの同僚と個人的な関係や最初の信頼関係が構築されていれば、容易にできることなのです。
現場形式の次の利点として、シミュレーションのボディランゲージが挙げられた。参加者からは、ボディランゲージを総合的に観察することで、より良い状況判断ができるようになったという声が聞かれました。また、会場型の利点として、空間内での移動が挙げられました。グループルームに歩いて行く、立ってエクササイズをする、フリップチャートに書き込むなど、ただ歩くだけでも身体のバランスが取れ、利点として認識されているようです。
また、オンサイト形式の利点として、フリップチャートの使用や、その場でスナックやドリンクが用意されていることが挙げられました。フリップチャートの使用については、その後のディスカッションでも興味深い点がありました。長年フリップチャートを使って仕事をしてきた人や、クリエイティブでビジュアルな表現が好きな人ほど、トレーニングやメディエーションにフリップチャートを取り入れたいと考えているようです。このような経験がない人は、フリップチャートに書き込むことに消極的で、メモやビジュアライゼーションを行うためのデジタルな手段を好みます。
また、各フォーマットのデメリットについても質問しました。全体として、デメリットの言及は、メリットに比べて半分程度にとどまりました。この違いは、参加者が両フォーマットに対して、全体的にポジティブな見方をしていることを示している。ただし、デメリットの質問には、オンサイト形式の利点とみなされるものが、同時にオンライン形式の欠点となることも多く、またその逆もあるということが反映されていることに注意が必要である。そのため、参加者はデメリットの質問を冗長だと感じて回答しなかったのかもしれない。
したがって、オンサイト形式の最大の利点が、オンライン形式の欠点として最も頻繁に言及されていることは驚くことではありません。コーヒーや休憩室での会話がなく、一般的に対面での接触がないことが、オンライン形式でのネットワーキングを難しくしていると認識されています。また、「移動がない」「画面を長時間見ている」ことも、2番目の短所として挙げられています。しかし、これをデメリットとする回答者は半数以下であった。調停シミュレーションのボディランゲージの欠如も、オンライン形式の短所として挙げられた。接続や技術の問題については、4つの言及がありましたが、これらはすべて、普段コンピュータを扱わない参加者が、新しいプラットフォームを学ぶことに抵抗があったことによるものです。オンラインと会場での比較デメリット 現地授業のデメリットは、オンライン授業のメリットの一部(全てではありませんが)も反映しています。15人の参加者が、旅費と経費を利点として挙げています。7人の参加者は、現場での授業はストレスが多いと述べています。ディスカッションの結果、参加者の中には、現地でずっと「ふるまわなければならない」と感じている人がいることがわかった。また、昼食時も他の参加者から離れられないという意見もありました。一方、オンライン授業では、カメラの電源を切り、静かに過ごすことができ、よりリラックスできる空間となりました。
オンサイト形式の最後のデメリットは、グループのダイナミズムについてである。(1)研修のディスカッションの場面で、一部の参加者が見落とされていると感じたこと、(2)一部の参加者は、個々の参加者が会話を支配し、発言時間が長すぎると感じ、「議論が手に負えない」といった発言があったことです。また、「現場にいると、特定の参加者が頻繁に発言するようになり、静かな参加者から反感を買ってしまう」と感じている参加者も何人かいました。しかし、発言頻度の高い参加者は、オンラインでは発言しにくいと感じていないことが重要な点です。したがって、デジタルなオンライン空間では、誰もがより平等に扱われていると感じたのです。

概要
結論から言うと、私たちが自発的に出発したわけではないこの旅は、非常に豊富な知識を与えてくれました。旧世界では考えられなかったことが、今では新しい現実の一部となっています。調停トレーニングの新しい形式が出現したのです。参加者とトレーナーのインタビューを評価し、調停トレーニングの参加者の相互作用を観察した結果、新しい形式としてのオンライントレーニングは参加者に非常に受け入れられ、調停者になるという目標を達成するために同様に効果的であると言えます。このことは、古典的なモデルの現場研修の場合も同様である。どちらの形式にも長所と短所があります。それを知ることで、形式を最適化することができるのです。
オンライン形式では、デジタルプレゼンテーションの形式、構成、自己反省のための練習、グループダイナミクスが肯定的に評価されています。オンサイト形式では、研修以外の参加者と話す機会、ネットワーク作り、動き続けること、他者のボディランゲージをよりよく理解することなどが特に高く評価されています。また、完全なオンサイト形式からハイブリッド形式、さらには純粋なデジタル形式へとトレーニングが開放されることで、グループの多様化も可能になります。会場での研修では、参加者は身近な環境からしか参加できませんが、デジタル形式では、地理的な制限はありません。 現在、世界中の調停協会、研修認証機関、研修機関が、将来的に何をどのように認めるかについて議論している。
残念ながら、個人的な利益や市場政策の考慮が、あまりにも多くの役割を担っています。"昔からこうだった "と言ってブレーキをかけ、古いフォーマットに戻るのではなく、始まったばかりのこの旅を続け、さらに新しい道を見つけ、試し、評価し、さらに改善することが望まれるのです。
COVID-19の時代に調停実務がどのように変化したかについては、初期の調査・研究5がある。現役の調停人の多くは、パンデミック終了後も、これまで以上にオンラインでの調停を続けることを想定している。調停訓練は、職業的現実のために調停人を訓練すべきであり、訓練機関の財源を満たすためのそれ自体が目的であってはならない。調停トレーニングの未来は、私たちの前に広がっています。新しい形式への柔軟性と開放性、そしてトレーニングの絶え間ない発展こそが、未来の調停者が要求し、またそれに値するものなのです。
オンライン調停トレーニングにご興味のある方は、ぜひご利用ください。
* 国際調停協会(International Mediation Institute)の認定を取得。
* 大学認定(国際経営学研究科)
* 12週間で40時間のライブオンラインセミナーを実施
* ビジネス、科学、心理学、法律などの経験豊かな紛争専門家がトレーナーとして参加
また、ドイツ語でMediation Trainingを行うことも可能です。
メディエーション・トレーニング・オンライン - 2023年冬
* 認定メディエーター養成講座(非常勤)(m/f/d
紛争解決と調停の専門家になろう!*。
* 当社の認定調停トレーニングは、仕事で紛争解決を扱う方で、専門的な調停トレーニングをオンラインで完了したい方を対象としています。