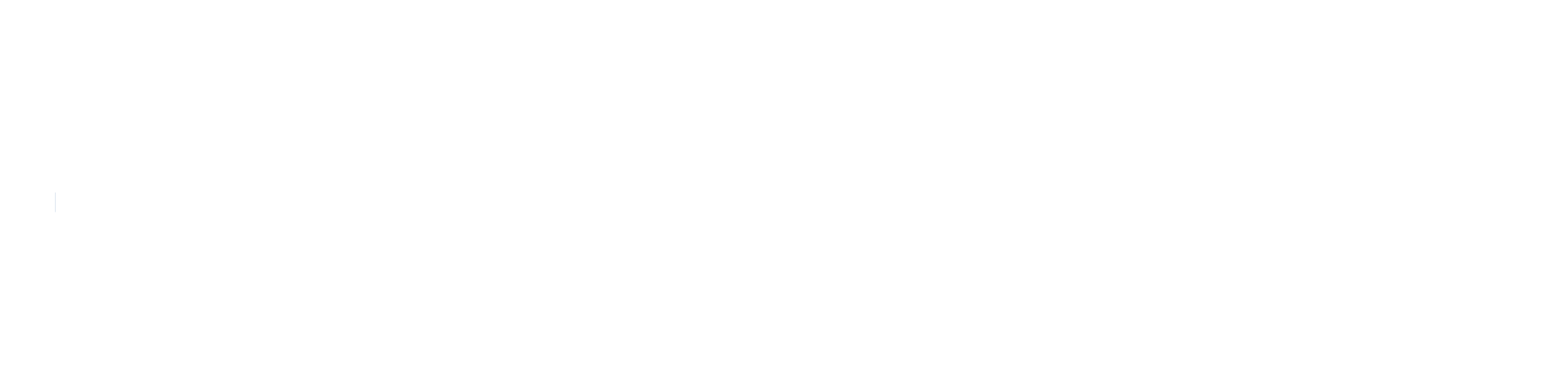調停は交渉を促進した。そうである以上、この2つの分野に厳密な境界線を引くことは不可能である。調停と仲裁は兄弟関係にある。実際、調停と仲裁の隔たりは非常に大きい。どちらも「任意」であるため「代替的紛争解決」(ADR)に分類されるが、任意性の基準は二国間であれ多国間であれ、対面交渉にも適用される。しかし、調停も交渉も和解を目指すものであるのに対し 当事者による仲裁は、その構造上、すでに伝統的な司法手続きに近似している。 第三者 を作る。 バインディング 決定 を適用することで合意に達した。 ほうそく.対照的に、この2つの側面は交渉にも調停にも見られない。従って、仲裁と調停を自動的に関連付ける一方で、伝統的な交渉を除外する我々の思考習慣は、本質的に欠陥がある。調停人は、自分たちの学問分野を誤解している。 概念的に位置する しかし、言うまでもなく、多くの調停者は弁護士でもある。
このことを念頭に置けば、調停者は交渉理論を次のようなものと見なす余裕はないことは明らかであろう。 テラ・インコグニタ.近隣の境界紛争など、低レベルで構造的に単純な調停には「理論的」な課題はないかもしれないが、紛争がより重く複雑になると状況は変わる。国際的な多国間紛争は、その性格が政治的なものであれ商業的なものであれ、言語や文化の多様性から生じる取引上の困難は言うに及ばず、連合の形成、問題の連結、サイドディールといった問題を投げかける。それだけでなく、個々の紛争は、両当事者が包括的な戦略的ニーズを視野に入れて取り組む可能性が高い。したがって、中長期的な要因が当事者の計算に与える影響もそれに応じて大きくなり、その一方で、内部の権力政治も紛争の軌跡に影響を与える可能性が高くなる。調停がこのような深海に足を踏み入れる場合、交渉理論における確固たる基礎が不可欠となる。

調停者が掘り下げることのできる膨大な文献が世の中にはある。しかし、国際交渉論の「教科書」としては、メディエーター志望者はチョン・ホウォン著の 国際交渉プロセスと戦略 (2016).紛争解決の学術的研究にすでに親しんでいる人々にとって、チョン・ホウォンはよく知られた名前である。ジョージ・メイソン大学の紛争分析・解決学教授であるチョン・ホウォンは、次のような経歴を持つ。 紛争後の社会における平和構築 (2005年)を出版して以来、教科書と編集集の両方からなる安定したアウトプットを続けている。そのタイトルが示す通りである、 国際交渉 が焦点を当てているのは、紛争解決全般の一部分である。しかし、まさにチョン自身の研究が平和創造の全領域を網羅しているため、彼のアプローチは、交渉理論に対する理解を深めたい調停実務家に特に適している。
国際交渉 すなわち、ゲーム理論に焦点を当てた「戦略分析」、交渉が行われる具体的な制度的・状況的パラメーターを扱った「交渉プロセス、行動、コンテクスト」、そして最後に調停と多国間交渉の複雑さを扱った「拡張と変種」である。チョンは調停が持つ変革の力についてよく理解しており、交渉理論の教科書は調停を扱わなければ完成しないことを認識している:「二国間の相互作用は、仲介者の介入によって変化しうる。その役割は、コミュニケーション・プロセスの単なる支援から、議論の促進、提案の策定、さらには交渉結果の操作にまで及ぶ」(17ページ)。
本書全体を読むに越したことはないが、学生や実務メディエーターにとって、隅から隅まで読む時間を確保するのは難しいかもしれない。各部分の簡潔な要約は、両者がどこに注意を集中すべきかを見極めるのに役立つだろう。当面は、Jeong氏の入門的な論考のサーベイにとどめ、この後の3つの詳細な論考の舞台としたい。
ネゴシエーションが人間関係においていかにユビキタスなものであるかを考えると、それについて「理論的」に時間を費やすことを正当化するのは、最初は難しく思えるかもしれない。結局のところ、歴史上ほとんどの交渉人は、教科書や資格などなくても、うまくやっていくことができたのである!要するに、答えはこうだ。 交渉は失敗することもある.そうなれば、結果は壊滅的なものになりかねない。従って、交渉理論家がまず理解しなければならないのは、交渉の成り行きに影響を与える要因が多種多様であることであり、成功を確実にするために努力する際には、それらを考慮に入れる必要がある: 「各交渉のさまざまな特徴は、アクターの意思決定システム、問題の特性(例えば、環境、貿易、安全保障など、協調行動の見込みが異なる)、相互作用の力学によって異なる。各当事者は、それぞれの目的を達成するための様々な課題に対処するための異種の能力と同様に、様々な外部システムの制約に直面する可能性がある。 (p. 4).
チョン氏が強調する2つ目のポイントは、成功する結果がどのようなものであるかを理解するためには、多くの場合、許容可能な範囲とは何かを認識することに依存するということである。 故障の程度 は当事者にとってである。すべての紛争にWin-Winの解決策があると考えるのはナイーブである。 対称的.むしろ、一方が他方より有利になるような結果の方が、和解が成立しないよりはましかもしれない。 "交渉問題は、非協力が非効率的で最適でない結果をもたらす場合に、2人以上のエージェントがどのように協力すべきかという文脈で理解される。" 成功には以下が含まれる。 を避ける 非効率的な最適でない結果』である。このように、チョンは私たちに次のことを求めている。 リアリスト.最良」の結果は、多くの場合、当事者それぞれの視点から見た「最も悪い」結果である。その解決策を見極める方法を学ぶことが、交渉理論が私たちに与えてくれるものなのだ。

だからといって、「Win-Win」の解決が不可能だと言っているわけではない。チョン氏は「統合的」アプローチと「分配的」アプローチという用語を紹介し、「Win-Win」が実際にはどのようなものなのか、よりニュアンスの異なる概念を把握できるようにしている。統合的アプローチは、テーブルの上の利益を拡大することで、すべての当事者の利益を追求するものである。例えば、生産性が向上した後に、資本と労働の間で分配される利益の増加などである(p.9)。ここで、価値創造は以下をもたらす。 絶対的利益たとえ 相対利益 は等しくない.ここでも、「Win-Win」は対称性を意味しない。というのも、統合の後には必然的に分配の問題に立ち戻るからである。たとえすべての当事者が相対的な利益が等しくならないことを認めたとしても、交渉解決における一方的な度合いというものは、依然として争われるべきものなのである。実際、私たち自身の経験から、当事者が最も強硬な態度を示しやすいのは、まさにその対象が損害の限定であるときであることがわかっている(「損失回避バイアス」の結果)。つまり「パイを大きくする」こと自体は、たとえ不平等な分配という事実が当事者によってすでに不可避であると認識されている場合であっても、答えにはならないのである。チョンの要約 "統合的戦略と分配的戦略が一つの交渉の中で相互依存的な構成要素となるにつれ、対立と協力のプロセスの中で、価値主張と価値創造の間に潜在的な緊張が生じる"
この二項対立に加え、チョンは各当事者の交渉範囲の上限と下限を表すために、「願望点」と「留保点」というカテゴリーを導入している(p10)。明らかに、願望点は各当事者が最も望む結果を表している。逆に、留保点では、当事者は「アウトサイド・オプション」を行使することを好む。合意はもはや有利ではなく、合理的な行為者は、一方的に行動して得られるものより少ない額を取ることはない。(ウイリアム・ユリーのBATNA(「交渉による合意に代わる最善の選択肢」)という概念を知っている読者もいるかもしれないが、チョンは彼の言う「アウトサイドオプション」の方が好きである)。譲歩が「直線的」な交渉範囲、すなわち2つの留保点の間に固定された交渉範囲内で行われる場合、和解は以下のようになる。 分配的.パイの大きさは決まっており、双方は最小限のスライスを獲得しなければならない。Jeongが指摘するように、実際には、たとえ原理的に最適解が見いだせたとしても、これは膠着状態を生む可能性が高い。その理由は、各当事者が相手の保留点を明確に知らないため、仮決済がその当事者に偏っているかどうかを評価できない可能性があるからである。駆け引き 可能性がある 膠着状態を打開するためには、どちらがより多くの譲歩を望んでいるかが明らかになる必要がある。 値切り交渉のコスト 各当事者にとって、例えば時間的なプレッシャーが原因である。しかし、値切り交渉のコストが無視できるほど小さい場合、相手の真の予約ポイントに関する情報の非対称性(相手の「交渉ポジション」とは対照的)は、簡単にデッドロックにつながる。
メディエーターに特に関係するもう一つの点は、明白なようでいて見失いがちなことである。 単なる相互作用ではないではなく、むしろ 相互作用のプロセスそしてそのプロセスは、相互作用がどのように展開するかを形作る。特に、相互の利益がどのように特定され、問題がどのように「パッケージ」されるかに影響する。調停者は、交渉が「パッケージ化」されたものであることを忘れてはならない。ファシリテーター 彼らの最も強力なツールは プロセスデザイン.このことは、効果的なイシュー・リンクを生み出すために必要なアプローチが交渉のライフサイクルの中で変化するという事実を考慮すれば、なおさら重要である。 直線的でない (p. 13).調停者は、行き詰まりと打開のサイクルが繰り返されることを予期しておかなければならず、実際、以前に合意したトレードオフが新たな争点に照らして再考されるようになると、ある程度の「後戻り」が起こるかもしれない。進展はスパイラルであり、直線ではない。
優れたプロセスデザインは、マクロレベルで交渉フレームワークの健全性を分析する方法と考えることができるが、必然的にミクロレベルの分析、すなわち交渉者間の相互作用を取り巻く直接的な状況によって補完されなければならない。明白な例としては 場所現代において、「オンライン」紛争解決と、伝統的な対面の話し合いと比較した場合の相対的な(不)利点という問題が明らかに提起されている。(「人間」の次元に焦点を当てることは、プロセス設計の不可欠な部分と見なすこともできるが、チョンは後者を包括的な「形式」と明確に結びつけている)。しかし、この二重の「マクロ-ミクロ」焦点は、「対外的」交渉は「対内的」交渉と同期させなければならないという意識によっても補完されなければならない。これは、「境界的役割の葛藤」と呼ばれるものにつながる可能性がある。自陣の利害関係者と相手側の代表者の間の「境界的役割」を占める者として、交渉担当者は、首尾一貫した、理想的には最適化された交渉戦略を実行すると同時に、自陣との関係で葛藤管理に取り組まなければならない。これに関連してチョンは、80年代のロバート・パットナムの研究以来、交渉はますます以下のように見なされるようになってきたと指摘する。 戦略ゲームとしてだけでなくとしてだけでなく 制度的・システム的制約を反映した社会的プロセス.言い換えれば、交渉の当事者は、(少なくとも)ステークホルダーとの関係において、コミュニケーション・チャンネルと権力依存関係によって制約を受ける。

交渉プロセスに対するこの包括的な見方が調停者にとって何を意味するのかを理解するためには、冒頭でチョンが提示した考え方、すなわち交渉を成功させるために交渉者が立ち向かわなければならない力の数の多さに立ち戻る必要がある。交渉が失敗する原因を明確に把握することで、調停者は交渉が成功するための可能な限り強力な状況に身を置くことができる。大まかに言えば、チョンは最適な交渉解決策を模索する上で、3つの潜在的な破壊力を挙げている: "複雑なモデルでは、交渉者は、相手の目標や戦略に関する限られた情報だけでなく、優先事項の競合や自国内の分裂から生じる制約、さらには交渉の内外の環境の変化への調整の必要性によって、首尾一貫した戦略を展開する上で多くの困難に直面する" (p. 15).この凝縮された文章を分解すると、3つの破壊的な力とは次のようになる:
- 相手の目標、特にその目標に関する情報の非対称性 予約ポイント (そして、後述するように、当事者の 優先発注 ゴールの);
- 党内の結束と合意形成の目標が欠如しているため、効果的な交渉戦略を実行する党の能力に深刻な影響を与える可能性がある。
- システム的なものであれ、エピソード的なものであれ、交渉プロセスそのものに外在する状況が投げかける課題。
これらのうち、後者はもちろん対処が最も困難であり、ある意味で交渉理論の範疇を逸脱している。最初の2つの要素に関連して、調停者がどこで違いを生み出せるかは明らかである。私たちは 国際交渉プロセスと戦略この2つの問題は、定期的に再浮上してくる。しかし、この2つの問題のうち、最適でない結果を生み出す情報非対称性の役割は、ゲーム理論に関する第1部で特に大きく取り上げられる。